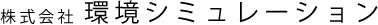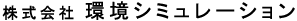世界一の大国の指導者は民主的な選挙で選ばれているようです。最近、選挙で新たな指導者が1回休みを経て選ばれました。選挙の勝利は、国の産業構造の変化の結果、困難な状況に追いやられた人々の支持拡大の結果とも言われているようです。その結果でしょうか、大国は、今までかなり鷹揚に他の困りごとを抱えた国々を助けてきた態度を大きく変えました。半世紀も前は圧倒的に豊かな暮らしを謳歌し、そのおこぼれを他国に分け与えてきたのに、「自国はこれまで自らの身を削ってまで、困りごとを抱えて国々を助けてきたのに、他国はその鷹揚さを傲慢にも当然のように受け入れ、自らの身を削ることなく、身勝手に大国を蝕んできた。」という態度を顕にし始めました。指導者自ら、「もうたくさんだ。もう他国の事情なんか知ったことか。勝手にしろ。我国は他国に依存なんかしなくても、一人で生きていける。これまでの恩義を感謝もせず当然のように受け入れ、我国から収奪してきた他国の事情なんか知るもんか」と口にし出してきました。そうかもしれませんが、「今まで、大国であることを良いことに、都合の良いルールを押し付け散々、甘い汁を吸って来たのに、今更、何を言うのか。」と内心は思いつつ、この民主的な選挙で選ばれた指導者に日参してなだめすかしているようです。大国さんよ、ちょっと苦しくなったといっても、知れているでしょう。我慢してくださいな。
指導者の選択は、その国の人々がおかれた状況によると思われます。少し強引かもしれませんが、状況の数値的評価は人々が感じている「幸福度」で表されるかもしれません。かの大国の指導者の選択は、人々の幸福度の悪化に由来するとも言えるかもしれません。人々の幸福度を表す指標は、たくさんあります。良く知られているのは、ギャラップ(Gallup, Inc.)による調査レポートを、国連の持続可能開発ソリューションネットワーク(SDSN)がまとめている「世界幸福度調査(World Happiness Report)」でしょうか。
「世界幸福度ランキング」は、新聞やニュースでよく引用されています。 日本でも良く引用されます。ここで示される幸福度は、自分の人生について可能な限り最高の人生を10、最悪の人生を0として、0から10までの11段階で、現在、自分がどの段階にいるかを評価するものです。対象となるのは、各国約1000人以上で、世界140以上の国々で行われています。更に、この幸福度の国別結果は、「一人当たりGDP」、「健康的な平均寿命」、「困ったときに助けてくれる友達・親族の存在」「人生で選択の自由」「寄付実施の度合い」「政府機関等に腐敗」の6つの説明変数で回帰分析し、それぞれの寄与度も分析されてランキング化されています。
2025年発表の世界のランキングは、ヨーロッパ諸国、特に高福祉で知られている北欧の国々のランクが高くなっています。ランキング一位は、フィンランドです。デンマーク、アイスランド、スウェーデンなどがそれに続きます。フィンランドは、11の段階中、7.736です。四位のスウェーデンは、7.345だそうです。米国は24位で6.724、日本は55位で6.147、お隣の韓国は58位で6.038、中国は68位で5.921だそうです。日本の幸福度評価に関する回帰分析では、「一人当たりGDP」と「健康的な平均寿命」の寄与が最も貢献しています。 ただし、それぞれの寄与の世界ランキングは、幸福度と同じで、それほど高いわけではなく、幸福度55位という日本の順位に対応しています。日本の幸福度評価に最も寄与の低いものが、「人生の選択の自由」です。この選択の自由という寄与は、ほとんどゼロで、世界ランキングの中では、最低レベル、140位程度となっています。
日本の人々の幸福度に対する「健康的な平均寿命」の寄与の値の世界ランキングがそれほど高くないことは問題です。実際、WHO(世界保健機関)の発表する世界の健康寿命ランキングでは、日本はシンガポールの73.65歳に続いて世界第二位の73.40歳です。この世界に誇る「健康的な平均寿命」の高さが、日本の人々の幸福度に対する寄与としては、あまり効いていないのです。WHO発表の「健康的な平均寿命」の第三位は、韓国の72.45歳です。アメリカは63.91歳で世界71位に比べ10年近く、健康で長生きします。韓国も、日本と同様、韓国の人々の幸福度評価への寄与が小さくなっています。
WHOの発表する平均寿命に関しては、日本は世界一位の84.46歳です。二位のシンガポール83.86歳に比べ、半年以上、長命です。第三位は、韓国の83.80歳です。アメリカは45位の76.37歳です。詳しい分析によれば、アメリカでの平均寿命は、所得水準や教育レベルが大きく影響しており、高所得で教育水準の高い人々はそれなりに平均寿命は高いのですが、低所得の人々が大きく足を引っ張っているということです。アメリカで社会的分断が顕なことは問題です。指導者の選び方に影響し、他国にもその影響が及びます。
日本の平均寿命が長いのは、新生児死亡率が低く抑えられており、ゼロ歳児の平均余命が特に長いことが寄与していると言われています。しかし、社会的分断がまだアメリカほどで顕著ではなく、所得の低い人々も長寿を全うできる福祉制度が効果を発揮していることが一因でしょう。しかし、公衆衛生や疾病管理水準が高く、身体的に健康に生きられる期間が長いにもかかわらず、日本の幸福度の世界ランキングがあまり高くないのは問題です。日本では高齢者も含め人々の生活、生甲斐に対する改善の余地が極めて大きいことを示唆しているように思われます。これらに大きく係わる社会や社会形成の基礎となる教育に対する改善が望まれているのでしょう。
多くの日本の人は、世界の人々に比べると、自分に人生の選択の自由があると思っていないようです。世界の幸福度ランキングにおいて、幸福度が11段階で、8に近い7なのか、6前後なのか、それほど差異があるようにも思えません。しかし、日本の人々は、世界に比べると、自分がそれほど高い段階にあるとは思っておらず、特に人生における選択の自由度に関して、悲観的に感じていることが、幸福度を下げている要因の一つです。これも社会や教育の制度が大きく係わっている気がします。
こうした世界ランキングでは、紛争当事国のランキングも気になるところです。ウクライナ紛争の当事国であるロシアは66位で5.945、ウクライナ111位で4.680、パレスチナ紛争の当事国であるイスラエルは8位で7.234、パレスチナは108位で4.780となっています。やはり戦況が優勢な国の方が少し高くなるのでしょうか。民の幸福度の世界ランキングが低いロシアが乱暴な振る舞いをするのもある意味、納得できる気がします。しかし不思議なことはイスラエルです。イスラエルの民の幸福度ランキングは世界10指に入るほど、高いにもかかわらず、パレスチナ占領地の民に、ロシア並みの振る舞いをする指導者のやり方には理解に苦しむところがあります。イスラエルは民主国家ですから指導者は民主的に選ばれている筈です。小規模な紛争を繰り返すインドとパキスタンも、お互い原爆の保有国のお隣どうしで気にかかります。パキスタンが109位で4.780、インドが118位で4.389です。どちらも、「一人当たりGDP」や「健康的な平均寿命」も低いので、幸福度も低いのでしょう。パキスタンの幸福度が少し高いのは、イスラムとヒンズーという宗教的、社会制度的違いが表れているのかもしれません。ランキングの最後位がアフガニスタンです。147位で1.364です。幸福度は、一つ手前の146位のシエラレオネの2.998の半分もありません。
ちょうど80年ほど前、世界一の大国を中心とする連合国に屈服し、その後、従属的ともいえる相互関係を結んできた日本国は、多くの恩恵をかの国からいただき、感謝も致しておりますが、今現在は指導者の交代を機とする露骨ともいえる大国の振る舞いに振り回されている気がします。かの国との深い相互関係を今更、縮小することは難しいことです。かの国の人々の幸福度が近年徐々に低下している原因は、かの国の事情が最も大きく、他国の寄与が多いとは思えません。しかし幸福度が下がったことで、その分、乱暴なふるまいも許されると考えて行動しているに違いありません。しかし日本は、まだまだ幸福度の世界ランキングでは、かの国に倍以上も後位となっています。かの国は、遥かに幸福度の世界ランキングが高いのですから、かの国の鷹揚さを期待してしまいます。振舞を自重して欲しいものだと思います。
今の時代、社会が発展し、複雑化してきています。あらゆる事象の相互依存関係が強くなっています。国と国との国際的な相互依存性を削ることは、かの国の指導者がどんなに無理押ししたとしても難しいことのように思えます。ましてや相互依存の範囲が極小的に見て、人と人のような小さな単位で見れば、相互の依存関係はより密になります。資源と人口を十分に抱えた大国は、他国との関係を縮小しても、あるいは十分幸福に生きていけると考えられるかもしれません。しかし分業化が進んだ現代では、人との関係性なしに生きていくことなどできそうもありません。人と人との相互関係を断ち切ることなど、どのように富んだ国でもできそうにもありません。ロビンソンクルーソーのように、離れ小島で1人、人との関係性なしに暮らすことなど、現代社会では全くの夢物語でしょう。例え、十分な資源のある離れ小島で1人、他人との関係性なく、暮らすことができたとしても、暮らしに必要となる様々な知識は、離れ小島に来る前に他の人々から頂いたものでしょうし、持ち込んだ様々な道具にしたってすべてを本人が一から作成したものではないでしょう。ほかの人との関係性があったが故に、1人で生きて行けたと言えます。国と国との関係性も、人の社会ですから、人と人との関係性の拡張でしょう。関係性を薄めて独自に過ごすことなどできません。
かの国の人々の幸福度が上がることが、かの国と他の国々との関係性を損なうことなく改善されることに繋がることを願っております。日本の人々の幸福度が、それほど高くないことは心配です。しかしあまり心配しなくても良いような気もします。他国から見ると日本の人々は、例外的な人もいるかもしれませんが、一般的には、温和で、優しく、控えめです。人から幸福度を尋ねられたら、たとえ、幸福度は高いと思っていても、控えめに答えるのが日本人の特性のような気がします。
乱流シミュレーション技術は、多くの人には限られた分野の自分には関わり合いの無いもののように感じるかもしれません。しかし、人々の間の複雑な関係性故に、すべての人々に何らかの繋がりをもっています。乱流シミュレーション技術も人の社会を支えており、欠くことのできないものです。すべての人、すべての国の人と繋がっています。