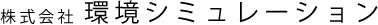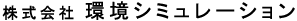うつろい(移ろい)という言葉を聞くと、どのような印象を持たれるでしょうか。「うつろい」は、字引によれば、物事が変化することや、時間の経過によって変わっていく様子を指します。例えば、季節の移り変わりや人の心の変化などが「うつろい」と表現されることがあります。時間経過のタイムスパンは、様々です。季節の移り変わりであれば、数か月、時間になおせば1000~2000時間程度での変化をいうのでしょうし、人の心の変化であれば、数日のこともあれば数年、十数年のこともあるでしょう。数日であれば100時間程度のタイムスパン、数年、数十年であれば、10,000時間から100,000時間単位での変化を意味することになります。時間の流れとともに景色が変化するのを見ることは、人の心に様々な感傷をもたらすことのように思えます。「うつろい」は、時間の経過による人に焼き付いた様々な印象の変化を表しているようですが、その際の時の経過の長さ、変化の速度は、様々です。「うつろい」に関して、印象に強く残っている電車をめぐる景色を挙げてみます。
最近あまり見かけない気もしますが、通勤電車など窓を背にしたロングシートで、幼い子供が窓に向かって座り、熱心に外を眺めている光景を良く見かけます。子供に付き添っている大人は、子供の靴が他の人の衣服を汚さないよう靴を脱せて、座席の上に正座もしくは膝立ちさせています。すいている電車に乗り合わせシートに座ることができると、中学に上がる前ぐらいまでは、まだ子ども扱いされますので、窓を背にして座らず、気兼ねなく窓から流れゆく外の景色を眺めることができます。座れそうもないときは、電車の運転室の仕切りのガラス窓部分に立って、運転席の前の左右に流れゆく外の景色を眺めるのも良いことです。流れる景色、移り行く風景は、子供には極めて魅力的です。「うつろい」の子供ながらの体験であると思われます。
大人でも電車に乗る際は、新幹線であろうと近郊電車であろうと、窓の外の景色の流れ、「うつろい」を見ることは多くの人には楽しいことと思います。この時、飛び込んできて飛び去っていく架線を支える電柱など近場を見ているわけではありません。少し遠くの穏やかに流れ来て、流れ去る景色を見ています。窓から強い日の光がさすと、日除けが下ろされてしまい、穏やかに流れる遠くの景色が見られなくなります。仕方ないとは言え、残念に思います。外が見通すことができて、日の光はさえぎる日除けにして欲しいと思います。建築用にはそうした日除けも開発されています。外が見えないという意味では、トンネルが続く地下鉄では、電車の外の景色を見る機会はあまりありません。しかし先頭車両に乗り込むのはお薦めです。運転室のすぐ後ろに立つのが良いです。運転室は運転席の背後は遮光カーテンでガラスの仕切りが隠されてしまい、前が見えませんが、運転席横のガラス仕切り前は、遮光カーテンが下ろされておらず、暗いながらも前照灯で照らし出されて流れる風景を見ることができることがあります。車掌室は、遮光カーテンが下ろされなくて、電車後方の景色が見られて良いと思われるかもしれません。しかし、前照灯に照らし出されるわけでもなく、また迫りくるのではなく、目の前から去っていく眺めはそれほどの魅力にはなりません。
外の景色を楽しめないときは、別の楽しみを見つけられます。筆者の場合、運転席室の中で、動いている計器を見ることに別の楽しみを感じます。刻々と表示を変える運転席の計器類も、窓の外の流れる景色同様に興味を引きます。発車から定速運転に至るまでと、定速運転から減速して停車するまでの変化の「うつろい」を楽しむことができます。
今は、運転席前の計器類もデジタル表示に変わってしまい、昔よく見た計器を今見ることはあまりありません。当時の運転席の計測器で、まず一番に目に付くのはブレーキの圧力計でした。たいていは2針です。黒の針は、ブレーキ用の圧縮空気の容器内圧力で、赤の針は、ブレーキシリンダー内の圧力を示していたと思います。運転手がブレーキをかけると、圧縮空気容器の内圧力を示す黒い針も若干揺れて下がりますが、赤い針は運転手のブレーキのかけ具合で、圧力を増していきます。その後、運転手が制動力を調整するため、かけ始めは強い制動を掛け、赤い針は黒い針と同じ圧力を示しますが、次第にブレーキシリンダー内の圧力を緩めます。時々、制動力を強めるため圧力を挙げることもあります。電車が停車した後、再びブレーキシリンダー内の圧力を少し上げて止った電車が動かないようブレーキをかけ続けます。電車はレールに若干の勾配があれば簡単に動き始めてしまいます。この停車時のブレーキシリンダー内圧力は運転手により違っていたような気がしますが、数気圧程度はかけていたような気がします。圧力タンク内の圧力は、筆者が覚えている限り、それほど高くなく5気圧程度(ゲージ圧、5kgw/cm2)だったような気がします。通常のガスボンベには大体150気圧程度のガスを封入するのに対して、ずいぶん低圧で、電車は止まるんだと感心した覚えがあります。
電車は架線から電気をもらうので、時代によりますが、運転席には電圧計や、電流計なども備えられていました。筆者が中学生の頃、利用していた電車は製造年が「大正」という古いものでした。乗降扉も自動ではなく乗客が手で開け閉めしていました。多分、昔の市電と同じだったと思います。手動扉ですので発車前には、車掌が扉の掛け金が閉まっていることひとつひとつ確認していました。しかし、時には電車の走行中に、扉が開いてしまうのも度々、見た覚えがあります。のどかなものです。古い電車ですので運転席の計器は圧力計だけでした。運転手がモータ―への入力電圧を調整するノッチのハンドルがどの位置にあるか、その際の電車の加速感はどれほどかということとともに、このブレーキの圧力計をいつも見ていました。大学に進学して東京に出てきましたが、さすがに大正時代製造の電車などにはお目にかかることもなく、運転席には、圧力計の他に速度計や電流計、電圧計もついていました。さすが東京の電車と感心した覚えがあります。電圧計は2つあって、架線からレールまでの電圧を測るものと、蓄電池の電圧を測るものでした。何のためか知りませんが、東京の電車は蓄電池も積んでいるんだと感心しました。架線電圧は1500ボルト、蓄電池電圧は100ボルトでした。
電圧計、電流計の針の「うつろい」を見たのも楽しい思い出です。架線電圧は電車の発車時には大電流が流れるためか、大きく変動します。100ボルト以上、低下したかもしれません。その後も針は変動していたと思います。電流計は発車時に最大となり、400アンペア程度を示していたと思います。相当な電流です。大体、運転席のある車両には駆動用のモーターがついていないことが多く、いったいどこの電流や電圧を測っているか不思議でした。多分よく利用した電車は8両ないしは6両編成程度の電車だったと思います。電流は架線からレールに流れる一編成すべての電車の合計値だったのかもしれません。大体600kWです。電車1両あたり乗車人員も入れて50トン、6両編成で300トンの通勤電車は、600kW、60秒程度の電力による仕事量は合計で36MJになります。この電力で加速すると、300トンの編成は、時速55㎞程度に加速される勘定になります。36M Jが大きいか小さいかは、解釈は人によって分かれると思いますが、それほどでもない気がします。石炭1kgの燃焼による発熱量はおよそ40MJ程度です。蒸気機関車の熱効率がどの程度が知りませんが、10%程度とすると、石炭10kg分の燃料消費になります。
そのころの電車は空気圧によりブレーキシューを押し付ける機械式ブレーキのほかに、電車のモーターを利用する発電ブレーキも併用していたと思います。電車のモーターが発電機として働き、発電機を回すための力学的な抵抗で、電車を減速させていました。発電された電力エネルギーは、電車の床下に設けられたたくさんの電気抵抗器で熱に変換されていました。停車した電車に乗り込むと、扉の下にも多分抵抗器があったのでしょう、立ち上ってくる熱気でムッとすることがありました。せっかく発電した電気を熱で捨てるのはもったいないということで、架線に電気を戻し、同じ架線下の他の電車に電気を使用してもらう仕組みの回生ブレーキを備えた電車も、筆者が大学生時代には首都圏を走るようになっていました。いずれにせよ、この発電ブレーキが作動すると電流計が動きます。発車時と同じく400アンペア程度に上昇したように記憶しています。しかし、停車時には発電ブレーキは効きません。空気圧ブレーキを作動させています。今でも発車時には、運転手が空気圧ブレーキを緩める際に生じる空気の抜ける音がします。
流れる景色の「うつろい」が見えなくても、電車の加速や減速の際の変化は1分、60秒にも満たない短い時間変化ですが、とても興味深く、楽しい「うつろい」になると思います。筆者は、この「うつろい」を楽しみましたが、筆者同様にこの短い「うつろい」を楽しんでいる人は多いに違いないと思っております。
目に見える「うつろい」が楽しいのは、人に限らず動物の脳の基本的な性質ではないかと思います。動物は変化するものに着目します。目で見えることは、動物が生存していくために最も有効な力になります。獲物を見つけ、これを捉えて捕食すること、あるいは捕食動物を発見し、捕食されないよう逃走するにも目で見えることの有用性は疑い有りません。しかし動物の脳の情報処理能力は限られており、目にするものすべてに注意を払うことはできません。目で見る視野の中で、位置を変えるもの、すなわち動くものに注意を払います。よく死んだふりをして捕食されるのを免れるという話を聞きます。脳の情報処理能力は限りがありますから、まず視野の中で動くものに注意する、脳神経が刺激されるようプログラムされています。動くものに着目し、本能的もしくは過去の経験と照らし合わせて、敵味方の区別や安全の確認などするわけです。動かないもの、風景の中の一部、背景になってしまったものに着目するには莫大な脳の情報処理が必要になり、なかなか実現できないものなのでしょう。動くものに対する気づきや興味、「うつろい」に対する印象の強さは、脳の情報処理に限りがあることに由来した動物の本能的な特性と言えると思われます。動物である人もその例外ではありません。動くもの、「うつろい」、に大きな関心と注記を払います。脳への刺激は、時間変化が急であるほど強くなります。時間変化が急なものに関心を持ち、対処しなければ、生存が怪しくなるという動物の本能が人に備わっているからでしょう。子供のみならず人が電車の窓から流れる景色を楽しむのも、この本能に根差していると思われます。
建築や都市の計画は、この空間の移動に伴う「うつろい」を大切にします。建築空間や都市額の中で活動する人々に、如何に「うつろい」を演出し、意識下でも無意識でもプラスになる印象を与えるかは、デザインの初心者から熟練したマエストロに至るまでの基本になります。話が飛びますが、街中を歩いていて、風の吹き方が気になることがあると思います。街中の風は、温度や湿度、あるいは明暗の明るさなどと違って、かなり局所的に変化します。例えば、高層ビルの周囲などは、高層ビルが風の通りを邪魔するため、その影響で風が強くなる場所や、弱くなる場所が、比較的、短い距離で生じてしまいます。人は変化、すなわち「うつろい」に敏感になる本能を持っています。場所の違いで、時間的にも、距離的にも近接した間隔で、風の吹き方に違いがあると、これを明確に検知し、風を意識します。強い風、弱い風を明確に意識し、強い風はさらに強く印象付けられます。強い風は驚きにつながります。安全よりは危険を認知します。高層ビル周辺のビル風の問題は、ビル風を認知する人の情報処理の仕組みにも大きくかかわっています。ビル風が環境問題にならないためには、変化が穏やかであることが本質的に重要です。移動に伴い、なだらかに「うつろい」、穏やかに変化する環境を人は楽しみます。ただ、逆説的ですが、まずは安全であることを認知していれば、驚きを生む大きな変化、急速な変化に人は喜びも感じます。部分的な強い風を楽しめるようにする工夫は、あり得るのではないかと思っています。