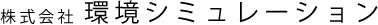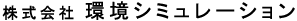流体中に設置された発熱する物体は、周囲の流体により冷却されます。流体が空気のように赤外線を透過させるものであれば、発熱体周囲の物体表面との赤外線のやり取りの結果、周囲物体温度が発熱体より低ければ実質的に赤外線放出の効果によっても冷却されます。流体と発熱体の相対速度が大きければ、一般に冷却効果が高くなり、発熱する物体は周囲の流体によってよく冷却されることになります。この原理を用いて、流体の速度を測定することが良く行われます。流体が空気であれば、発熱体に対する空気の冷却力から、発熱体周辺の風の速度を測定することができます。熱線風速計やサーミスター風速計は、このような原理を用いて風速測定を行います。
この熱線風速計やサーミスター風速計の測定原理を詳しく知ることができれば、それだけ信頼性の高い測定ができることが期待できます。そうした意味もあり、しばしば、測定原理に関する解説を目にします。筆者が、経験上、これらの解説を見聞きして、あまり触れられておらず、疑問というほどではないですが不思議に思った事項があります。良い機会かと思いますので、ここで、少し考えてみたいと思います。
最初の疑問は、放射による放熱の影響です。結論から言えば、影響はある筈です。ただ、影響を小さくすることはできると思われます。発熱方式の風速計で測定する場合、周囲が雪景色で、周囲の地物からの発熱体が受ける放射受熱量が小さそうな場合と、気温が40℃を超すような真夏で、太陽もカンカンと照り付けて、地面のアスファルト温度も60℃を超えるような場合とでは、熱線やサーミスターなど風感部の発熱体からの実質的な放射失熱量が違わないかと疑問を持たれるかもしれません。発熱体からの放射による失熱は発熱体の表面積と表面温度に関わります。発熱体の表面温度が変化しないのであれば、放射による発熱体からの失熱量は周囲の影響を受けません。しかし発熱体が周囲の地物から受熱する熱量は、周囲状況で変わります。これは地物からの放射放熱量を代表させる指標の一つである平均放射温度で表すことができます。平均放射温度が、発熱体の全周を取り囲む仮想の全球で評価されていれば、発熱体周囲から発熱体が受け取る放射受熱量は、この平均放射温度と発熱体の表面積で求まります。発熱体の表面積が十分小さく、またこの平均放射温度と発熱体自身の温度との差が大きければ、発熱体からの放射失熱に対して、周囲物体からの放射受熱は相対的に十分に小さくすることができます。逆に言えば、発熱体に関する放射受熱、失熱の影響を小さくしたければ、発熱体は小さくした方が良いし、発熱体の温度は周囲の環境温度に比べ大きな差となるよう高くした方が良いことになり、更に放射失熱量を発熱体の発熱量に対して常に一定割合として変動させないようにするには、発熱体の温度を一定とするよう制御することが有効と思われます。
疑問の一つに発熱体のサポートへの伝熱の影響があると思います。結論的に言えば、これは場合によって大きな測定誤差の原因となり得るので注意が必要になります。発熱体をサポートなしで空中に浮かせておくことはできません。発熱体の温度を測定しなければなりませんし、発熱体を発熱させるためのエネルギーを供給しなければなりません。発熱させるためのエネルギーは、主に電気エネルギーでしょうから、発熱体に給電する必要もあります。しかし、このサポートは曲者です。サポートは主に金属で作られることが多いと思います。電気エネルギーを供給しなければなりませんし、発熱体の温度を測定するため、温度との関係性が良い電気伝導度(電気抵抗)を測定しなければなりませんから。しかし、電気をよく通す物体は、熱もよく通します。発熱体からは、空気中への熱伝達の他、放射熱伝達や、このサポートへの熱伝導があるわけです。この発熱体サポートへの熱伝導は、サポート自身からも周辺空気への熱伝達が生じることを意味します。風の影響もうけるわけです。このサポートから空気中に失われる熱が、発熱体自身から空気中に伝達されて失われる熱に比べて、十分小さく、大きな影響を与えないこと、特にサポートと風向の相対的な位置関係でサポートから空気に伝導される熱量が大きく変化しないことが必要になることが想像されると思います。熱伝導ですから発熱体とサポートの温度差が、サポートへの熱伝導量の大きさの指標となります。サポートの温度がサポートと風向の相対的な位置関係で、変動しないことが必要です。残念ながら、多くの熱式の風速計では、この発熱体のサポートが測定対象の風に対して、垂直方向か、水平方向で、測定値に少なくない影響が出るようです。もちろん、サポートの形状以前の問題として、発熱体の形状、たとえば、発熱体が球体であるか、あるいは円筒状か、あるいはワイヤー状かで、発熱体と風の方向によって空気中への熱伝達が影響を受けることはもちろんです。実際の測定では、この発熱体の形状とその風向との位置関係が、最も重要で、これを正しく(風速計の使用法の記載に正しく対応させるという意味で)することが最も重要です。しかし、その発熱体を支えるサポートも発熱体と同様に風の方向によって影響を受けることを忘れてはいけません。
もう一つ疑問があります。重力の影響です。これは特に熱式の風速計で1m/s以下の低速の風を測定する際に気を付けるべきことになります。重力の影響というと分かりにくくなりますが、浮力の影響といった方が良いかもしれません。発熱体から空気に熱伝達されると空気は温められ、熱膨張して密度が小さくなり、浮力が生じて重力と反対方向に移動します。つまり、発熱体の周りの空気は、たとえ周辺の空気が動かなくても(風がなくても)、上部に向かって流れる自然対流(プリューム)が生じています。発熱体自身が、測定したい空気の流れを乱してしまい、上昇気流を生じさせてしまうわけです。もっと言えば、発熱体は、自ら発熱してその周囲に自然対流(プリューム)を生じさせて、この流れによって自らを冷却しているわけです。風速の測定装置自身が、測定すべき風を乱し、風を作り出していると言っても良いかもしれません。上昇気流は、空気に伝達される熱量が大きいほど強くなることが予想されます。発熱体の周囲に生じてしまうサーマルプリュームが測定しようとする空気の動きに比べ小さくなるようにしなければなりません。これは発熱体に供給される電気エネルギーに対応しますので、発熱体への電力供給が小さくなる発熱体形状と電気抵抗が求められることになります。経験的に現在よく使われている熱線風速計やサーミスター風速計は、測定したい空気の速度が0.5m/s程度以下になると、発熱体周囲に生じる浮力プリュームによって冷却される割合がおおきくなり、測定したい風の速さと発熱体から空気に伝達される失熱の関係が複雑になり、正確な測定が難しくなります。
発熱体を利用し、風の冷却力を頼りに風速測定を行う方式は、上記の他にも例えば、発熱体への電力供給を正確に測定する工夫や、発熱体の温度測定を正確に測る工夫など様々な工夫が必要になります。これら電気的な測定も調整が正しく行われていなければ、正確な測定を妨げる要因になります。熱式風速計の測定原理の解説の多くは、ここに注力して解説している印象があります。
熱式風速計は、前述した3つの要素以外にも多くの誤差要因があります。結局、正確な測定を行うためには、既知の様々な速度の風に、この熱式風速計を曝して、その際の風速計のメーターの読みを記録し、メーターの読みと実際の風速を比較して、校正曲線を得ることが基本になります。関わる要素が多すぎて、理論的に校正曲線を求めることは非常に困難だと思います。しかし、この既知の様々な速度の風を作り出すことも難しい課題になります。少しくらい位置が異なっても、同じ速度である風を作ることは難しいことです。3桁の精度を要請すると言って、速度の揺らぎが1/1000以下の均一な風を作るのはかなり至難な課題です。筆者が知っている一番良い方法は、空気が静止していることが確かな状況下(例えば温度揺らぎが小さい両端を閉塞した地下トンネルなど)で、移動速度が正確に測定できる台車に風速センサーを固定してのせ、その移動速度と風速計のメーターの読みから風速計の校正曲線を得ることのように思われます。実際にこのような方法で風速計の校正曲線が求められた例があるか否か、筆者は知りません。
室内や屋外の3次元空間の中の任意の測定点の風速を測定することが必要になることがあります。3次元空間の中で風速の空間分布が予想される場合です。測定点とした場所に、正確に風速センサーを設置することは、かなり困難な課題になります。3次元空間の中で誤差1/1000の精度で位置合わせすることは、結構しんどいと思われます。3m×3m×3mの室内空間で多くの測定点で、位置精度誤差1/1000以下で測定するとした場合、許容される位置設定誤差は、3次元方向それぞれで3mm以下にしなければなりません。レーザー計測など、かなりの技を使用しないと位置決め誤差3mmは達成できません。風速センサーの数も問題になります。多くの測定点で測定が必要な場合、測定点の数だけ風速センサーを用意できれば、位置決めは1回で済みます。しかし風速センサーを多数用意出来ない場合は、風速計は一つとし、風速計のセンサーをそれぞれの測定点に移動させ位置決めし、空間内でセンサーを移動する際に乱された流れ場は落ち着くまで待機する時間が必要になります。莫大な労力が必要になります。位置決めが一回だけで済む前者の場合、風速計の校正曲線を風速計の数だけ用意する必要があります。風速計の風速センサーの形状が似ていても、校正曲線が同一ということは、ほとんどあり得ません。多点の風速測定は大変な労力が必要となる作業です。
CFDの出番と思われる方も多いと思います。実験でも実測でも、実際の空間で風を正しく測定することは、いやになるほど大変なことです。それに比べCFDは、実に容易に多点の位置の風速を出してくれます。風速センサーを用いた実際の風速測定はすたれ、CFD予測が、ますますはばを利かせる時代になっています。でも忘れないでください。CFDは、多くの場合、乱流モデルとモデル方程式を基礎にしています。また計算条件も、実際の境界条件を極めてシンプルにモデル化したモデル化された条件で解かれることが多いと思われます。筆者などは、必要となる労力にうんざりしたことも多かったですが、リアルに風速測定を行うことはそれなりに好きで、楽しみでした。