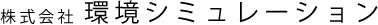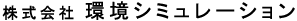風の速さは、風速計で測ります。ものを測る際は、その測り方が問題になります。昔は、重さや長さ、嵩を測るにしても、測り方が必ずしも統一されて厳密なものではなく、測る人によって、測られた値に差が生じ、再現性がなく、様々な問題を引き起こしてきたことが思い出されます。
ものの速さはものが移動した距離をそのものが移動に要した時間で除して求めるのが、速さ(速度)の原理に即した測り方と思います。移動した距離や移動に要した時間の測り方も、速さの測定結果に影響を与えますので、統一された方法で測定される必要があるのはむろんです。屋外の風であれば、風と一緒に流れると想定された風船などの目印となるものに関して、その移動距離と移動時間から、測ることが分かりやすいかもしれません。昔、屋外の風速を測るのに良く使われた4杯型のロビンソン型風速計も、この空気の移動距離を測定することをその測定原理としていました。4個の半球型(お玉杓子型とも言えますでしょうか)の風杯の回転が空気の移動に追従することを期待したものです。地上を走る車の速度の測定と同じ原理を使っています。車のタイヤは、地面との摩擦により、滑ることなく、車の移動距離をタイヤの回転数で測ることができます。移動距離が分かれば、これより車の速度が求まります。今、実際に街を走っている車の速度計の多くは、このタイヤの回転数(もしくはタイヤの回転数に対応するプロペラシャフトなどの回転数)などに基づいて、速度が求められていると思います。もっとも最近は、人工衛星からの電波により車の位置座標を算出し、車の位置座標の変化から移動距離を割り出して、速度を求める方法も用いられているようですが、電波の届かないトンネルの中でも速度を測らなければならないので、タイヤの回転数は、まだまだ利用されているようです。
ロビンソン風速計の4個の風杯と風との関係は、道路面とタイヤの関係に類似させられますが、タイヤは道路と接地面のみで接触しており、車の移動に対するタイヤの回転の関係は、滑りがない限り、安定していますが、ロビンソン風速計の風杯の回転と風による空気の移動は、タイヤの回転と地面の関係のように単純ではありません。風杯が風の中を回転する際は、風杯の半球(お玉杓子)が風の向きと同じ方向への移動するのは、ほんの一瞬だけです。風杯が一回転する半分の時間、風杯の半球は風の向きと同じ方向に移動しますが、回転のため、風とはハス(斜め)の方向に移動します。しかも、残りの半分の時間は、風の向きと逆方向に移動します。回転により、風の向きと同じ方向に移動する1回転の半分の時間は、風杯の半球(お玉杓子)が風を受ける形になります。風の移動方向に対する風杯の移動速度は、ゼロからスタートしてゼロに戻る半回転の間、そのほとんどは風による空気の移動には遅れる移動速度となり、風を受ける形になります。従って、風杯の回転を加速する加速力が働きます。残りの半分の時間は、風杯の半球(お玉杓子)は、風の向きと逆方向に移動し、半球の外側で風を受け流す形になります。風杯の半球(お玉杓子)に働く力は順方向に移動する際より弱くなりますが、風杯の回転を減速させる負の加速力が働きます。風杯の回転は、この風を受ける方向の回転を加速させる力と風とは逆方向に風杯の半球が移動する際の回転を減速させる力が釣り合った状態で回転することになります。ロビンソン風速計の風杯の回転が、車のタイヤの回転と同じように、空気の移動を正確にとらえているか否かは、少し怪しいことは、すぐに理解されると思います。しかしながら、問題はありますが、昔は、ロビンソン風速計で、空気の移動距離(これを風程と称していました)が測れるものと仮定して、風速を求めていました。筆者は子供のころ、通っていた小学校で、このロビンソン風速計の実物を見て、風速計のメーター内にたくさん並んだ歯車が、確かに移動距離を表していることを確認し、風は、雲が移動するように空気の塊が移動していくことであることを実感しました。
現在では、ロビンソン風速計のような四杯型の風速計は、姿を消してしまいましたが、風速変動に対する追従性能の高い三杯式のカップ風速計は良く用いられています。三杯式風速計では、風杯の回転数が風速と単純な関係(回転数と風速の校正曲線がほぼ直線となる関係)となることを原理としており、もはや風による空気の移動距離(風程)を測定する機器として用いられているわけではないようです。風により風杯を回転させて、風の速さを測る風速計と似た風速計として、風車型風向風速計(エエロベーン風向風速計)があります。この風車型風向風速計は、プロペラ飛行機のプロペラのような風車が、垂直尾翼のみ残され、主翼や水平尾翼のない飛行機のような風向計の先端についた形状をしています。この風車型風向風速計は、気象官署での公式な風速、風向の測定器となっていますが、風速の測定原理は、三杯式風速計と同様で、風速を検知する風車の回転数により風速を測定するものです。もちろん、ロビンソン風速計で仮定されていたような、風程(空気の移動距離)を測定するというような思想に基づいたものではありません。ついでながら、風環境に関わる人々への注意が必要になりますが、風の観測データを利用する際は、風速測定に用いられた風速の測定機器の確認が必要になります。後で述べる超音波風速計が用いられているなら、それほど心配はいりませんが、風速測定が風車型風向風速計によるものであれば、風速2m/s以下の弱風時の風速測定には慎重な配慮が必要になります。例え、気象庁の検定済み(校正済み)の風車型風向風速計が用いられたとしても、風速計の測定精度は、一般に風速2m/s以上で保証されたものと言われます。風のパワーは、風速1m/s以下になると大変微弱で(1m/sで0.6W/m2ですので受風面積が0.01m2程度では、6mW程度)、摩擦などの機械的ノイズの影響を免れません。弱風を測れる三杯風速計でも風速1m/s以下の測定データに関しても慎重な扱いが求められます。
ところで空気の移動距離を測定し、これより速度を直接測定することが難しい場合は、間接的にこの空気の移動速度を測ることが考えられました。そうした方法の代表的な例として、空気中を伝搬する音波を利用することもよく行われています。空気中の音の伝搬は、空気自身の動き(風速)と静止空気中の音の伝搬の重ね合わせですので、音の伝搬速度から風速を測定することもよく行われます。風速を測りたいところで、決まった距離をおいてスピーカーとマイクを向かい合わせて、音の伝搬時間が測れます。その際、スピーカーとマイクの位置を入れ替えて音の伝搬時間を測って、両者の差を取れば、音の静止大気中の伝搬時間がキャンセルされて、両者間の空気の移動のみの寄与による音の伝達時間を知ることができ、その間の空気の移動時間、すなわち風速が測定されます。音の伝搬時間の測定から風速を測定する方法の長所は、三杯式風速計や、風車型風向風速計では計測できない、1m/s以下の弱い風を正確に測定できることです。エレクトロニックスの発展のお陰で、3方向の風速ベクトルの測定の可能な超音波風速計も、風車型風向風速計とそれほど変わらない価格での入手が可能となってきました。室内などの風速1m/s以下の正確な風速測定に苦労してきた筆者などは、時代の進歩に感慨を覚えます。
気象観測や室内空気の流れ性状の解析に、あまり使用されませんが、ピトー管による動圧の直接測定に基づく、風の測定も良く行われます。航空機は、翼周りの空気の流れが、航空機を浮揚させる揚力などに直接関係するため、航空機周りの風の流れの把握が常に求められます。特に離着陸時など、航空機の対気速度が小さく、航空機を浮揚させるのに必要な主翼に生じる揚力に余裕がない場合には、対気速度の把握が重要になります。この際に最も活躍するのがピトー管です。ピトー管は単純な構造の二重管で、二重管内側の管の端部が開放された全圧測定孔となっており、二重管外側のリング管に、全圧測定孔より下流部分に静圧測定孔が複数設けられており、ピトー管内管部分が全圧、その外側のリング管部分が静圧を受けるようになっています。ピトー管の内管の全圧測定管部分と外側のリング管の静圧測定部分に圧力を導く、導圧管を接続して差圧計に導き、両者の差圧から求められる動圧から、ピトー管に対する相対的な気流速を求める構造となっております。ピトー管による空気速度の測定も、動圧がある程度以上(通常、数m/s以上)ないと正確な測定はできないようです。またピトー管は、流れが物体で遮られる澱み点で生じる全圧とピトー管表面に設けられた静圧孔で正しく静圧を評価できるよう、ピトー管が流れに対して正対、すなわち傾いていないように設置しないと正確な測定はできません。傾きの問題よりさらに基本的な注意になりますが、航空機に設置されたピトー管は、全圧測定孔、静圧測定孔が、きちんと空気の流れに開放されていないと正しく航空機の対気流速度を測定できません。しかしながら、航空機の整備(洗浄など)の都合で塞がれたり、菅中に結露や他の理由で液水などが入り込み、氷結して詰まったりすると、当たり前ながら正しく機能しません。過去、これが原因の一つとなって墜落事故などの重大事故を引き起こしたことが複数回ありました。ピトー管による気流速度は、差圧計を除けば、可動部など機械的な故障を招く要素もなく、最もロバストな気流測定法の一つと思いますが、それでも測定を誤り、重大事故原因となることがあるようです。
風の速さを、空気に放熱している発熱体の放熱量で、測定することも良く行われます。もっとも、伝統的な風の測定法は、カタ温度計ではないかと思います。これは、鉱山などの労働環境の快適性を見積もる際の風速の測定器として、今から100年ほど前にイギリスで考案されたと言われています。カタ温度計は、人体に対する風の冷却力を測定することを意図して開発された温度計で、球部の表面積を大きくしたガラスの温度計です。使い方は、カタ温度計を38℃以上に温めてから環境中に放置し、カタ計の示度が38℃から35℃まで下がる時間を測定します。カタ温度計の目盛りに示された値(カタ係数)を冷却に要した秒数で割るとカタ冷却力(カタ度、カタ値)が得られ、この冷却力と環境温度から気流速度が求められました。カタ温度計は、日本では昔、JISによる標準測定法も定められていました。しかし、現代では容易に熱線方式の微風速計が用いられますので、JISは廃止されたそうです。
微風速の測定は、ピトー管による比較校正などが可能な高風速における測定と異なり、微風速ゆえに風速計の校正は難しい課題です。カタ温度計による風速測定に限らず、微風速計の測定の正確さを評価するためには、特に測定の正確さを常に評価するための校正が必要になります。様々な校正法が提案されていますが、最も原理的に確実な方法と考えられるのは、移動速度が一定に保たれた装置を静止空気中に設置し、その装置の移動速度を気流速度として、風速計を校正するものです。腕が一定速度で回転する機器に、校正したい風速計の風感部を設置し、風感部の移動速度を気流速度として校正する方法が良く用いられました。カタ温度計による風速測定には、この方法が用いられました。ただし、疑り深い人たちはそうした回転装置は、周囲の空気が静止せず、回転に合わせて移動するので、正しく校正できない可能性を示唆しています。そうした疑り深い人達の究極の提案は、使われなくなったトンネルとトンネル中を移動するトロッコの使用などがあります。具体的にはトンネルの両方の口をふさいで、空気の流れない静止状態を作り、そこを校正すべき風速計を乗せたトロッコなどで移動させて、その移動速度が、気流速度になるという方法で校正するものでした。微弱風速の校正は、なかなかに難しい課題なのです。
熱線風速計は、風による冷却力から風速を測定するため、この風速計の校正法が正確な測定に重要となります。特に微風の測定が問題になります。今回は、紙面が尽きてしまいましたので、また別機会に述べてみたいと思います。