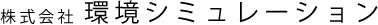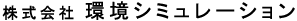前回のコラムでは筆者が大学院で大変苦労したというお話しをしました。今回は大学院時代の基礎的研究に一区切りをつけて、T建設で実務的研究を行い始めた頃のお話をしたいと思います。
T建設では風洞を新設中であったため筆者はまずはこの風洞実験担当として入社することになりました。余談ですが、入社式翌日から当時の新入社員の恒例行事であった1週間の自衛隊研修に参加しました。人生初とも言える起床から就寝まで「超」規則正しい自衛隊生活を経験しました。(この自衛隊研修は数年後、時代に合わないとのことで中止となりましたが。。)その後、東京の某作業所で半年の現場研修を経験しました。現場では毎日深夜までの残業や職人さんとのバトル等、大学院時代とはまた別の意味で苦労しましたが、建設業の最前線でもある建設現場での経験や得た知識はその後の研究員生活においても大変役立ちました。
半年の現場研修を経てT 建設の研究所に配属になり予定通り風洞実験を担当しました。新設であったためまずは風速プロファイル(高さ方向の風速分布)の作成や静圧勾配等、風洞の基本性能の確認から始めました。ここではやや話が固くなりますが、静圧勾配について少し触れたいと思います。風洞模型実験は大気境界層中の風(自然風)を再現した状況下で行なう必要があります。実際の建築・都市スケールでの大気圧は一様と考えられるため境界層風洞内の静圧も一様である必要があります。しかし風洞の断面積が一定であると境界層(地表の影響を受け高さ方向に速度分布が生じる層)を発達させた場合、静圧に勾配(流れ方向に不均一)が生じます。従って厳密にはこのような状況下での実験では正しいデータが得られません。この問題はブロッケージ問題(風洞断面に対して模型の見付け面積が大きいと誤差が生じる)と同時に生じるため大変複雑です。これらの問題を回避するには風洞内の天井を可変とし、更に模型は極力小さいものにする必要があります。(一方測定精度の観点では模型は大きい方が良いのは当然です)当時この静圧勾配が及ぼす誤差について少し検討しましたが、筆者は結局その後数値シミュレーションに軸足を移したため、この問題の決着を含め風洞実験を行う機会はその後大きく減少していきました。これは古巣のT大M研究室の研究活動の影響を強く受けたことによるものです。
そのころM研究室では風洞実験を追い越す勢いで「数値風洞」の開発が行われていました。数値風洞の意義として「従来の実験が自然現象の1部を切り取ってこれを観察するということであったのに対して 数値シミュレーションは人工の自然の作り出すことに成功したといえる」 という恩師のM教授の言葉は大変説得力があるものでした。
詳細は略しますが、当時としては最先端の数値風洞(CFDシステム)が開発されました。
現在では数値風洞という言葉はほとんど耳にしませんが現状の CFD解析システムは、実際の風洞実験で可能なことはほぼ計算できるという意味で、コンパクトに数値風洞化されているものとみなしてよいように思われます。
尚、当時のM研究室には民間各社から優秀な研究者の方が共同研究員として数多く参加されていました。初期の段階ではNK設計のK氏、S建設のH氏、K 建設のI氏等です。K氏は高次の乱流モデルを、H氏は主に屋外のLESを、I氏は一般極座標を用いた解析を研究されていました。筆者は各氏と同じく民間会社の研究員だったこともあり当時からたびたび情報交換等させていただいていました。
数値風洞開発には、風洞実験の知識以外に流体力学的、数学的、コンピュータ的の3つの知識が必要と言われています。これらをオールラウンドに持ち合わせている研究者は数少ないですが、M研究室では上記の各研究員がM先生やK先生のご指導の下、相互に上記の知識を補完しあっていたため結果として「数値風洞オールラウンドチーム」が形成されていました。M研究室の数値風洞はその後数多くの成果を生み出していったことは言うまでもありません。
当時筆者はこれら各社&各氏の活動を横目で見ながらT社独自の実務用数値風洞の構想を練っていたところ、風洞関係ではなく別の分野から強力な追い風が吹いてきました。
「クリーンルーム」の登場です。ここから筆者のCFDの実務への本格的展開が始まりました。これらについては次回のコラムでお話したいと思います。