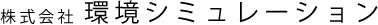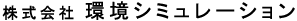筆者の古巣のT建設が新しく風洞を建設しました。旧風洞は筆者が入社した頃建設されましたので、約36年ぶりの新型風洞実験施設ということになります。新風洞では断面の拡大とともに「風の見える化」を適用したリアルタイム風圧可視化システムやCFD結果の同時表現システム等が特徴です。従来風洞模型実験とCFDは代替関係(ライバル関係?)でしたが筆者は常々風洞とCFDの結果の組合せ(おいしいとこ取り)が有効と感じていました。この新風洞は実験と可視化&CFDが一部連動したハイブリッド型になっています。本システムは,風圧計測を行いながら結果を任意の視点から動画表示できます。また,別途CFDで得られた風速分布も同時に可視化できるため,風の流れと風圧の変化を併せて考察することも可能なようです。
筆者は6年間の大学院時代及びT建設入社の頃は主に風洞模型実験を行っていましたので風洞には特に思い入れがあります。その後研究はCFDに比重を移していきましたが、CFDを行う際にもこの風洞実験の経験が非常に役立っています。そこで本稿では風洞模型実験とCFDについて述べてみたいと思います。
ご存じのように、風洞模型実験で実物の再現を試みるためには「相似則」の適用が必要になります。相似則は模型則とも呼ばれ、幾何学的に相似な二つの流れが力学的にも相似内になるための条件です。
では具体的には何を相似にすればよいのでしょう?模型ですので建物群は当然幾何縮率に従って相似形になります。問題は目に見えない風洞内気流ですが、むやみに風を模型に向かって流すのではなく、風洞気流性状も実際の風と相似にする必要があります。従来より国際的には①平均風速の高さ方向分布、②乱れの強さの高さ方向分布 ③乱れ(渦)の「大きさ」の再現が提案されてきました。③はスペクトル解析を行って求めますが筆者はこの再現にずいぶんエネルギーを注力した記憶があります。しかし現在では③は省略されることが多く、通常は①,②を再現して実験を行います。建築学会発行のCFDのガイドラインでも風洞実験の条件として①、②を採用しているようです。
風洞実験の精度については従来から様々なベンチマークテスト(同一条件で各機関が気流や風圧の実験を行い結果を相互比較)が行われています。筆者もいくつかのベンチマークテストや同一模型を用いた国際共同研究に参加したことがあります。結論から言えば一般に想像するほど実験間で結果は一致しません。特に単独模型周りの気流分布は一致の程度が相対的に低いと言えます。CFDの検証では単独模型実験結果を用いることが多いですが、模型実験結果自体もばらつくことを感触として理解しておいた方が良いかもしれません。ただしケーススタディのような複数模型は建物群がクリアーな境界条件となるため結果は一致しやすいと言えます。
また、模型実験では実際の風観測と異なり風向一定状態を継続できるため、建物模型周りの気流性状を詳細に検討できます。筆者は平均値や乱れだけでなく建物周りの「風洞気流の頻度分布」を求めてみたことがあります。興味深いことに建物近傍ではいづれの場所でも(正規分布ではなく)ワイブル分布で近似されることがわかりました。(実際の風の強風の出現頻度がワイブル分布で近似されることはよく知られていますが)また風洞気流の平均値を求める際の誤差も理論的に検討しました。結論から言うとある変動する風データから平均値を算出する際の標準誤差は平均化時間と乱れ(渦)の大きさの関数になります。渦が大きいほど、また風が弱いほど、観測時間が短いほど誤差は大きくなります。これは模型実験でも実際の観測でもCFDでも同様です。もし瞬時値をその平均値とみなすと理論上統計誤差は場合によれば100%を超えることにもなってしまいます。これらの知見は現在CFDを行う際にも大いに役立っています。
最後になりますが、従来では顧客が風洞実験見学に来られても風は見えないため、結局「模型見学」の範囲で収まることが大半でした。冒頭にのべたように一部ハイブリッド型になったことは顧客への現象説明等本分野の推進に一役買うものと期待できます。 風洞実験においても可視化やCFDとのハイブリッド化を通してICT化が大きく進んでいるようです。