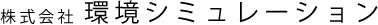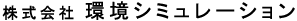子供のころ、痰唾を吐く意味を不思議に思っていました。よく映画の一場面で喧嘩を売る場面などで唾を吐きかける場面があります。殴りかかるのであれば、物理的に危害を与えられるので喧嘩の開始として理解できますが、唾を吐きつけても物理的な危害は与えられないのにと不思議に思いました。しかし、映画の場面のつながりからは、唾を吐きつける行為も、人に敵意を示す行為の一つであることを学習した気がします。子供のころ、仲間同士の喧嘩を傍で見ていた記憶がありますが、罵りあいや取っ組み合いは覚えていますが、唾を吐きつけあったのは見た覚えがありません。もう一つ、不思議だと思ったことがあります。筆者の子供のころ、瀬戸物の蓋付の白い痰壺を駅や病院の待合などでよく見かけたのにいつの間にか消えてしまったことです。
痰壺は日本の専売特許ではありません。ヨーロッパは知りませんが、アメリカ映画の西部劇でも痰壺は出てきます。少し古い映画(もう40年ぐらい前ですが)ですが、名車デロリアンを改造したタイムマシンで1985年から1955年の30年前の過去や2015年の未来、1855年の100年前の過去に旅して様々なドタバタを繰り広げるハリウッド映画がありました。「Back to the Future」 のPart1,Part2,Part3の3部作です。面白いので、時々ネットで繰り返し見ています。このPart3は1855年代のアメリカ西部でのドタバタが主題です。主役の少年が悪役とトラブルになるきっかけとして、悪役が酒場の痰壺の中身を頭から浴びるシーンが挿入されています。酒場のテーブルの脇に痰壷がおいてあり、お客が適時、唾を痰壺に吐き出していたことが分かります。1955年代や1985年代のシーンでは痰壺はなかった気がします。いずれにせよ、1855年代のシーンで悪役が痰壺の中身を浴びるシーンを違和感なく見て笑えるということは、少なくとも1985年時代のアメリカ人やこれが上映された多くの国々で、痰壺が酒場などの公共空間に置かれていたことの意味は理解されていたということなのでしょう。
もう一つ、唾にまつわる記憶があります。もう四半世紀以上も昔の話ですが、日本を訪れた中国からの旅行者が、日本では街角で唾を吐き出す人を全く見かけないのに、母国で普通に皆が唾を吐きだしている。日本の街角でそうした人を見かけたとしたら、それは同胞であって、とても恥ずかしい・・・とか、雑誌か何かに書いてありました。確かにそのころ、筆者が中国に旅行すると、痰壺もあったような気がしますし、街中で人々が所かまわず、唾を吐き出していたような気がします。(筆者の記憶違いであったらごめんなさいね)どうして今の時代、人々は、唾を吐き出す行為をしなくなり、街から痰壺は消えたのでしょうか。不思議です。
最近はAIブームです。PCやスマホでAIに質問すると、なんでも答えてくれます。唾を吐き出す行為に関して、AIに聞いてみるのがよい気がします。MicrosoftのDeepな利用者なので、付属のAIシステムであるCopilotさんにお伺いしてみました。Copilotさんは、次のように答えられました。「こんにちは。ご質問ありがとうございます。人が他人に唾を吐きかけられると不快に感じる理由はいくつかあります。まず、唾液は体液の一種であり、他人の体液が自分に触れることは衛生的に不快です。唾液には細菌やウイルスが含まれている可能性があり、感染症のリスクがあるためです。」この答えは、正鵠を得ていると思います。コロナ禍を思い出すまでも呼吸器系の伝染病の多くは、唾液の飛沫で伝染していきますから。衛生の知識に疎かった昔も、咳などで飛び散る唾液が感染のもとと思っていたことでしょう。さらに答えます。「また、唾を吐きかける行為は攻撃的で侮辱的な行動と見なされることが多いです。これは、相手に対する尊重や礼儀を欠いた行為であり、社会的なルールやマナーに反するため、不快感を引き起こします。」筆者としてはこの唾を吐きだす行為が本能的に疎まれているのか、あるいは人の社会的な関係性から後天的に生じたのかが知りたいところですが、そこまでは答えてくれません。しかし、大小便を考えてみると答えが出せそうです。頭が正常なら人前で欲求のおもむくまま大小便を垂れ流すことなどとてもできません。便所で用を足します。このことから演繹すると、大小便と同じく、人前で唾を吐き出すという行為を忌むのも本能的というより、社会的に学習した結果のように思われます。
唾を吐きだす行為に連想してもう一つ不思議があります。日本語には、昔から「唾をつける」という表現があります。その意味は、唾を付けで自分のものであることを他の人にアピールすることだと思います。これは唾を吐きだすという行為と何らかの関連があるのでしょうか。「唾をつける」行為は、犬や獣が「おしっこ」でマーキングして、自分の縄張りを主張するように、人も昔は唾を吐きだして、自分のものであることを主張したのかもしれません。他人の唾もしばらくすると特有の匂いを感じます。良い匂いであることはありません。どちらかといえば、他人の唾の匂いは、いやな気分になりますから。この匂いで自己の権利を主張したのかもしれません。唾の匂いに関連して話を変えます。日本の人々はあまり人前ではしない気がしますが、世の中には「接吻(キス)」という行為もあります。これは、「唾をつける」という行為と何らかの関連があるのでしょうか。目的か、結果か、わかりませんが、接吻は相互に唾を交換することに繋がります。唾液の交換は、唾液にはフェロモンや免疫情報が含まれており、接吻を通じて互いの健康状態や遺伝的適合性を無意識に確認する役割があるという解説を何かの本で読んだことがあります。本当でしょうか。だって、唾には細菌やウイルスが含まれ衛生上の大きなリスクがあるとMicrosoftのCopilotが言っていました。
唾の交換は、「唾をつける」という意味と同じで、接吻の相手に唾をつけることにより、相手を自分の支配下すなわち接吻の相手を自分のものとして確認することかもしれません。さらに言えば、相手の唾を受け入れることにより、自分が相手のものになる(支配下に入る)ことを求めているのかもしれません。(これはCopilotなどが言ったことではありません。筆者の解釈です。少しマゾ的ですね。念のため)接吻での唾液の交換は互いの支配を受け入れる行為かもしれませんが、好きでもない人との唾液の交換には嫌悪が生じそうです。更に、唾を吐きかけられることは、好きでもない人と接吻することの嫌悪に増して、極めて不快になります。これは、相手の支配意識からの、敵意や軽蔑を感じ、自己の尊厳が傷つけられることにつながるのでしょう。だから、人は他人に唾を吐きかけられると不快に感じるのでしょう。
唾を吐きだす行為についてCopilotにお伺いを立てたついでに、痰壺がなくなった理由も伺ってみました。「ご質問有難うございます。痰壺が見かけられなくなった理由には、いくつかの要因が考えられます。主に以下のような変化が影響している可能性があります。その1. 衛生観念の向上:かつては痰を処理するために痰壺が使われていましたが、衛生面の配慮から公共の場や家庭での使用が減少しました。その代わりにティッシュや紙製品を使って処理した後、密閉できるゴミ箱に捨てる方法が一般化しています。その2. 医療技術の進歩:呼吸器系の病気に対する治療法や予防策が進歩し、痰を頻繁に処理する必要性が減少しました。そのため、痰壺の需要も低下したと言えるでしょう。その3. 環境配慮:痰壺が陶器や金属などで作られていたため、処理や廃棄が環境負荷を増加させる可能性がありました。この点で使い捨て製品の普及が影響しているかもしれません。その4. 時代の文化的変化:過去の生活習慣や風習が変化するにつれて、痰壺のようなアイテムも歴史の中に取り込まれ、使われなくなったと考えられます。多くの人にとっては痰壺自体が時代遅れのアイテムと認識されている可能性があります。痰壺についての話題、少し懐かしい気もしますね。他にも「昔はこうだったのに最近は見かけないなぁ」と感じるアイテムや風習があればぜひお聞かせください。」というお答えです。
Copilotも「昔はこうだったのに最近は見かけないなぁ」と感じるアイテムや風習の一つとして、痰壷を見かけなくなったこと捉えていました。筆者としても、Copilotの挙げた理由を少なからずは納得するところですが、このCopilotの答えには、一番大事な理由が欠けている気がします。それは、唾であろうが、痰であろうが、公共の場で、唾を吐きだす行為は、「たとえ相手が、痰壷であっても、唾を吐きだす人が攻撃的で侮辱的な行動をしていると見なされる」ということに尽きるような気がします。その昔、中国からの旅行者が、日本では街角で唾を吐き出す人を見かけることはほとんどなく、見かけたとすれば、それは同胞の旅行者で、とても恥ずかしい場面だと感じたことが、もっともよく表しているように思えます。むかしは粗野で礼儀知らずの人が多かった時代には、唾や痰を公共の場でも吐き出す行為が行われていましたが、文化的で洗練された現代では、人に不快な印象を与えかねない、唾を吐きだす行為は自重されるようになったということだと思います。Copilotは、この時代時代の何が粗野で何が洗練された行為なのかという点に関する人々の意識の変化を見落としてしまったのでしょう。この点昨今の筆者らが使い得るCopilotはまだまだ幼いのかもしれません。
唾を吐き出す行為に関して延々と述べてきましたが、唾と同様に人が排出するものに呼吸で吐き出す息があります。この息も人から吐き出されますが、他の排出物と少し違います。大小便や痰や唾は、衛生上の理由や社会的な理由によりますが、特定の場所に排出されます。排出物に他の人が手を触れること、ましては、それを自分の体内に摂取することはありません。しかし人から吐き出された息は、他の人がその幾分かを吸う可能性があります。もちろん自分自身も一度吐き出した息を再び吸い込む可能性があります。自分の痰唾や大小便を再び摂取することなど考えられませんが、吐き出した息は再摂取が可能です。満員電車などを思い出してください。あのように密集した状態では、自分が吐き出した息や、他の人が吐き出した息を、呼吸で吸う可能性がないとは言えないでしょう。人の吐き出した息をみんな吸っているわけです。子供の喧嘩の捨て台詞で、「お前の吐き出した息を俺が吸わないようにしろ」という言葉を聞いたことがあります。TVドラマや映画の中での喧嘩の捨て台詞だったと思います。喧嘩した相手に、「二度と俺の前に現れるな」的な意味があるのでしょう。「お前の吐き出した汚い息を俺に吸わせるのか?」という脅しなのでしょう。
筆者は、この人が吐き出した息を他の人がどの程度吸うのか興味を持ったことがあります。具体的な検討課題としては、人が吐き出した息を吸わない間合いを考えることでしたが、より具体的には喫煙者のタバコの煙を非喫煙者が吸い込むpassive smokingの防止のための検討でした。その後、タバコの煙に限らず、人の呼吸により吐き出された息が室内にどのように広がるか、また人が呼吸により吸い込む空気は、人の周辺からどのように集められるかは、室内の衛生上の一つの課題の一つとして検討しました。この際、役立ったのがCFD(空気流れの流体シミュレーション)でした。CFDは、人の「呼吸空気質」の研究にとても役立ちます。人の吐き出した息だって、タバコの煙だけでなく、匂いや炭酸ガス、更には感染性の微粒子などが含まれています。室内空気には、建材から放散される揮発性の化学物質や、他人が吐き出した匂いや感染性の微粒子がなど含まれています。このように汚れた空気を人は呼吸で吸っているのです。実験的にこうした人の呼吸空気質を調べることは、骨の折れる作業になりますが、CFDはこれを簡便にかつ詳細に行うことを可能にします。CFDの威力、様様でした。