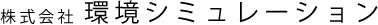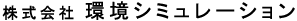日常何気なく利用している鉄道がどの程度の人を輸送しているのでしょうか。朝のラッシュ時、いったいどれ位の人が電車に乗っているのでしょうか。実際に計算してみます。街で良く見かける今時の通勤電車は、一両当たり左右に4つずつのドアがあり、その間に7人掛けのロングシートがあります。一両当たり6つのロングシートで42名、車両の端には3人掛けシートが4つあり、12名、合計、54名が一両当たりの座席数です。電車には座席シートの他、立っている人がつかまるための吊り輪があります。この吊り輪の総数と座席数の合計で乗車定員が決まっているような気がします。混雑していないとき、暇に任せて観察したところ、およそ座席数の倍以上はあったように記憶しています。通勤電車一両あたり、およそ150人程度が定員といったところでしょう。電車の車掌室をのぞき込むと、各車両の乗車率を表示していることがあります。時々のぞき込むと、ひどく混んでいる印象で180%から200%ぐらいになっていました。ひと昔前、身動きできないほどの混み具合では300%に達するといいました。国電(国鉄が存在した時代の通勤電車の総称)ならぬ酷電と称されていたようです。300%の乗車率は、一両あたりだいたい500人弱の人が乗っていることになります。すごいですネ。筆者が昔、通った高校は50人学級が1学年に10クラス、一学年500人でした。結構なマンモス高等学校の1学年分の生徒全員が一両の電車に乗っている勘定で、凄みを感じます。この混雑では、電車から降りるのも乗り込むのも大変です。乗り込むときのコツは、ドアの上の框を掴んで内側に倒れこみ、自身の体重も利用して足と手を使って押し入ることです。降りるときも同様です。倒れこむ動作で前の人達の隙間に入り押し進むわけです。座席には座らない方がよかったと思います。座席に座ると、人の支えがありませんので座席に向かって人が倒れこんできます。座席前で立っている人も倒されないよう手近のものに手をつきます。筆者は急な揺れで手をつく動作で、誤って座っている人の顔をパンチしたことがあります。幸い許してもらえました。不意の揺れで、窓ガラスに手をつき、窓ガラスも割れました(昔のガラスは今と違って薄かったのでしょう)。べニア板で応急手当がされて、運転が継続されました。通勤時間帯が終わると、ホームや電車の中に片足だけの靴が散らかっていたといいます。ぎゅうぎゅう詰めではかがみ込むことなどできようもなく、脱げ落ちた靴を拾うなんて、とてもできませんでした。
通勤電車の一両の長さは20m程度、車両の幅は3m未満、2.8m程度と言います。電車の床面積は56㎡程度といったところでしょうか。300%の乗車率、身動きできないほど混雑している電車では、1m×1mの場所におよそ10人の人が詰め込まれていたわけです。ちなみに、2001年に兵庫県明石市で発生した群衆雪崩では、事故現場の歩道橋での人口密度が1㎡あたり13~15人に達していたとされています。一般に、事故が起こる可能性がある混雑時の人口密度は、1㎡あたり5~6人以上だそうです。300%の乗車率は1㎡あたり10人ですから、群衆雪崩寸前の危険状態だったことになります。現代でも乗車率が200%近くなることがあるそうですが、そうした電車に乗り合わせると、急ブレーキなどの大きな揺れがあれば、倒れて踏んづけられて怪我をしたり、あばら骨が折れたり、窒息したりするリスクがあるわけで、それでも乗り込む人は、こうしたリスクを承知しているということでしょう。
朝のラッシュ時は短い間隔で電車が運行されます。例えば東京の地下鉄千代田線は、1時間に20本、約3分おきに電車が駅に到着します。一列車は10両です。一車両当たり300人程度は乗車している感じですので、一列車当たり、3000人もの人を運んでいる勘定になります。一時間では6万人もの人を運ぶ計算になります。一時間でさほど小さくない都市(人口6万人程度)の全員を移動させる量を一つの鉄道路線が輸送している勘定です。
自動車は、どれぐらいの人を運んでいるのでしょうか。自動車は、ある程度の車間距離をとります。高速道路や国道、地方道で違うかもしれませんが、車両速度にかかわらず、平均2~3秒に1台の車が通行しているといいます。時速50km/h ですと秒速14m程度ですので、2秒間隔ですと車間は20m強、時速100 km/h、秒速30m程度ですと車間は60~90mぐらいで、2~3秒に1台の車が通過するというのは、それほど外れていない気がします。これから考えると一時間当たりの車の通過台数は一車線当たりおよそ1500~1800台程度ということになります。これは高速道路でも地方道でも変わりないと思われます。ただし平面交差の交差点がありますと、信号機などで通過できない時間が生じますので、一車線当たり700~900台程度の容量になると思われます。アメリカなど鉄道があまり利用されず自動車交通が主な通勤・通学手段となっている地域では、いくらライドシェアが奨励されてもせいぜい2人/1台当たりの乗車人数ですから交通信号のない一車線の道路での移動人数は1時間当たり3000人強ということになります。片側2車線の道路で6000人/h、アメリカや中国などは道路整備により片側6車線(側道1車線を加え、両側で14車線、車道の道路幅50m程度)で、片側で2万人/時程度の人を運ぶことが可能なようです。鉄道は複線でも8~10m幅ですから、鉄道の交通容量は、面積的に見ても少ない面積で大量の人を運ぶ圧倒的能力を持つことが分かります。
こうした輸送を考える際に大事なことがあります。輸送は保存が成立しているということです。運ばれる人が輸送の途中で増減がないことが輸送の大原則です。物の輸送でも、託された荷物は輸送の途中で紛失したりしてはいけません。輸送の途中で勝手に分岐して、期待した場所とは違う場所に行ってしまっては輸送に信頼を置くことができません。鉄道にしろ、道路上の車による輸送は、途中に分岐点がない限り、同じ量が輸送されます。これは、電線を流れる電流であろうと、上水道を流れる水道水であろうと下水道で流れる下水であろうと同じです。輸送は入口から出口に向かってから途中で、失われることなく輸送されます。しかし世の中には、出発点と到着点の間に分岐があり分岐点で輸送量の増減があることはよくあります。分岐のない一方向のみの輸送はまれです。輸送路に有限の分岐点があり、網の目状のネットワークを形成していることはよくあります。鉄道ネットワーク、道路網、配電のネットワーク、上水や下水あるいは地域冷暖房の冷温水配管のネットワークなど、様々なネットワークがあります。物の輸送だけではありません。情報の伝達路もネットワークを形成します。分岐点と分岐点の間をつなぐ情報路の中では情報量が保存されます。しかし、この分岐点が有限ではなく、無限にあるネットワークでの輸送を考えることはそれほど容易ではありません。分岐点が無限ですので、通常の有限の分岐点を持つネットワーク解析で輸送解析はできません。
室内や屋外の気流は3次元的な複雑な循環流を形成しており、流れによる輸送は、移流によるものだけなく、拡散もあります。それこそ無限の分岐点を考えなければなりません。有限の分岐点を持つネットワークシステムで、3次元的な複雑な様相を呈する流れ場をモデル化して、輸送量に関して解析するには限界がありそうです。こうした複雑な流れの中で、着目する点から別の着目する点までの輸送量や、着目する点からその周辺への輸送量をどのように評価するか、興味ある課題だと思いませんか。
建物内外の空気の流れは、熱や汚染物質、あるいは清浄な空気を輸送します。この空気の流れは、流体シミュレーション(CFD)で解析することができます。多くの場合、流れ場解析は、この空気の流れによる輸送の結果を解析することを目的とします。空気の流れは輸送の原因で、熱や汚染物質、あるいは清浄な空気の空間分布や時間変化は、輸送の結果として生じます。輸送の原因となる流れ場の平均流速分布や圧力分布、あるいは乱れによる拡散係数分布に目を凝らしても、流れの輸送能力が分かる人はあまりいないと思います。3次元の空間分布を持つ、速度の等値線図や速度ベクトルに目を凝らしても、流れがどのように熱や物を輸送する潜在能力を持つかといった性質は、俄かに理解できません。流れの方向などで定性的な性質は、何となくわかる程度でしょう。ものの理解は結果をもたらす原因を理解することが求められます。原因を詳しく分析できれば、必要となる結果をもたらすにはどのようにすればよいかを合理的に考えることができます。結果を見て原因を考えることはできないことではありませんが、順序が逆であることは否めないでしょう。
流れの輸送能力を把握することが重要だと思います。室内や屋外の複雑な流れによる輸送にかかわる技術者は、この流れの輸送能力を何とか評価したいと考えていると思います。残念ながら(筆者としてはそれほど残念でもありませんが・・・)、現在のところ、輸送能力の評価は、流れ場自身の解析ではなく、解析された流れ場、あるいは実際の流れにトレーサーを混入させて、そのトレーサーの挙動(輸送された結果)から探ることに落ち着いています。ただ、強調しておきたいことは、トレーサーの混入を特定の地点だけで行っても、その特定の地点からの輸送能力しか見ることができないということです。3次元的に複雑な流れ場の全体の輸送能力を見るには、流れ場のあらゆる場所でトレーサーを混入し、それに対応するトレーサーの挙動をすべて観察することが必要とされます。真面目に行うと大変な手間になることは疑いありません。ただ、トレーサーの混入は、その特定の地点が周辺に対するある程度の代表性を持つものであれば、有限個数の特定地点からのトレーサーの混入で、流れ場全体の輸送特性をある程度把握することは可能です。(代表点の選定は、その周辺でのトレーサー混入とそれほど違わない応答が得られることが条件です。言葉を変えると代表点の周辺ではトレーサー混入の場所を変えたことによる輸送特性の変化が小さく、場所を変えたことによる感度が鈍いということに対応)を考慮して減じることは可能でしょう。
トレーサーの混入による流れの輸送能力の解析は、トレーサーの混入を入力して、流れによるトレーサーの応答を見ることで達成できます。流れの中で、注目する特定の地点にインパルス状もしくはステップ関数状もしくは三角波状にトレーサーを注入し、流れの様々な地点で、そのトレーサーの強度(濃度)の時間変化を観察すれば、トレーサーを注入した地点から、トレーサー強度(濃度)の時間変化を観察した地点までの、流れによる輸送能力を評価することができます。
全体的な流れの輸送能力を評価したければ、流れ場の代表性のある地点で、このトレーサーの注入に対する流れ場の各点での応答を調べればよいわけです。大変な手間が必要になりそうですが、着目する2点間の流れによる輸送性状は、トレーサーの注入に対する時間応答の取得で、得られるわけです。
筆者は、昔、危険物質放出によるテロの脅威が叫ばれたとき、有限な観測点でのみ危険物質の濃度を観測し、その観測値から、この応答関数を用いて逆解析することにより、危険物質が放出された場所と危険物質放出の時間経過を特定すること可能であることを実証したことがあります。